[サステナビリティ紀行]化学物質から子どもを守る~身近にあるプラスチック問題を知ろう~
2024/05/30
海ごみの問題や SDGs の普及でプラスチック問題が注目されています。石油由来の製品ということで地球温暖化につながっていますし、ごみ問題としても身近な話題ですが、プラスチックにはさまざまな化学物質が使われていることも注意しなければなりません。化学物質問題に取り組まれている NPO 法人ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議(JEPA)の成嶋悠子さんにお話を伺いました。
質問1:JEPA では化学物質の問題に市民の立場から取り組まれていますね。まず団体概要や特徴、最近取り組んでいる主な活動などを教えてください。
JEPAは、1998年9月に、全国158名の女性弁護士が呼びかけ、これに応えた50名の学際的発起人と約1000名の市民とともに設立されました。有害化学物質汚染の最大の被害者は、物言えぬ野生生物と未来世代の子どもたちです。JEPAは、彼らに成り代わって、予防原則に基づく有効な危機回避策を具体的に提言し、その実現を目指す国民的組織として結成されました。さまざまな領域の人々が、利害や立場を超えて結集し、知恵を出し合って適切な政策提言を行うことにより、広く世論を喚起して、政府に有効な対策を実現させることを目指しています。
具体的な活動の中心は、政策提言活動とその実現のためのロビー活動です。その活動の一環として、情報収集・調査研究活動、セミナー・講演会・学習会の開催、市民への周知・啓発活動、署名活動、国会議員や政府関係者、担当省庁、マスコミ、学会等へのロビー活動等を行っています。また、収集した情報を市民向けのブックレットやパンフレットとして刊行したり、HPでも公開しています。
最近では、PFAS(有機フッ素化合物)問題や、農薬再評価問題、プラスチックに含まれる有害化学物質の問題等に取り組んでいます。
質問2:今回、UNEP の報告書「プラスチックに含まれる有害化学物質ー要約と主要なポイントー」の翻訳版を作成されたとのことですが、内容について教えてください。
海洋プラスチック汚染をはじめとするプラスチック汚染が問題となり、2022年3月には、国連環境総会において、プラスチックのライフサイクル全体を規制する条約を策定することが決定されました。条約の具体的内容については、5回の政府間交渉会議(INC)で議論されることになっており、本年4月にカナダでINC4が行われたところです。11月には、韓国で最終のINC5が予定されており、条約交渉の動向が注目されています。
プラスチック問題に関しては、プラスチックの生産量の削減や、使い捨てプラスチックの削減、循環経済への移行が目指されていますが、リサイクルの輪の中に一度有害化学物質が入ってしまうと、有害化学物質を排除することは難しく、安全なリサイクルとは言えません。本報告書は、見過ごされがちなプラスチックに含まれる有害化学物質について、科学的知見を提供し、プラスチックに含まれる有害化学物質に対処するための緊急行動を呼びかけ、また、プラスチック条約の交渉を支援することをその目的としています。
本報告書によれば、プラスチックは多種類の化学物質から作られており、最近の研究では、13,000種類以上の化学物質が、プラスチック製品の生産に使用されたり、プラスチック製品から検出されているということです(本報告書5~6頁)。これらの化学物質のうち、①難燃剤、②有機フッ素化合物(PFAS)、③フタル酸エステル類、 ④ビスフェノール類 、⑤アルキルフェノール類・アルキルフェノールエトキシレート類、⑥殺生物剤、⑦紫外線安定剤・紫外線吸収剤、⑧金属・半金属類、⑨多環芳香族炭化水素類、⑩その他の非意図的混入物(NIAS)の10種類の化学物質のグループが、重大な懸念がある物質として取り上げられています(同7頁、表1)。また、優先的な取り組みが求められる10の産業セクターとして、①玩具などの子ども向け製品、②包装(食品接触材料を含む)、③電気・電子機器、④自動車、⑤合成繊維素材、⑥家具、⑦建築資材、⑧医療機器、⑨パーソナルケア製品・家庭用品、⑩農業・水産養殖業・漁業用品を挙げています(同8頁、表2)。これらの懸念化学物質が、プラスチックのライフサイクルの各段階で、プラスチックから放出され、人の健康や環境に悪影響を及ぼし、さらには、循環経済の進展の妨げともなると指摘されています(同9~11頁)。そして、このようなプラスチックに含まれる有害化学物質に対処するため、早急な取り組みが必要であるとし、具体的な対策を提案しています(同12~14頁)。
質問3:子どもケミネットという団体とも連携して活動しているとのことですが、どのような活動をされていますか? SDGs に関連した取組みもあれば教えてください。
子どもケミネットは、昨年4月に、JEPAが中心となり呼びかけを行い結成されたネットワーク組織で、全国の生協や、NPO・NGO等の団体、個人が加盟しています。学際的な専門家の方々にアドバイザーにご就任頂き、指導・助言をしていただきながら活動しています。この4月に1周年を迎えました。
今、ぜん息・アレルギーの増加、発達障害児の増加、不妊・不育症の増加など、子どもたちの発達や健康は、重大な危機に直面しており、これらの原因として、体内のホルモンや神経伝達物質による情報伝達をかく乱する人工の有害化学物質の関与が指摘されています。しかしながら、日本においては、こうした有害化学物質に対する規制がほとんどとられておらず、世界の国々に大きく後れをとっている状況です。このような状況を放置することはできないと市民が立ち上がり、結成されたのが子どもケミネットです。
子どもケミネットは、環境ホルモンをはじめ子どもの発達・健康に有害な化学物質について、国内外の研究・対策の最前線を学ぶとともに、立法・行政に対し必要な規制等の対策の実施を働きかけることを目的としています。有害化学物質についての国内外の研究に関する学習会の開催、及び、有害化学物質による子どもの発達・健康への悪影響を防止するために必要な対策に関する政策提言とその実現を求める活動を行っています。具体的な活動内容については、加盟団体から世話人を選出し、世話人会で決定しています。また、個別の課題については、プロジェクトチームを立ち上げて、課題に取り組んでいます。
本年度は、上述のプラスチック条約に関して、生産量の削減と有害化学物質の規制を各国に義務づける条項が盛り込まれるよう、日本政府に提言するとともに、署名活動を行い、11月に韓国で開催予定のINC5までに提出する予定です。さらに、提言の実現を目指して、国際NGO・IPENの下で、INC5の会合にNGOとして参加し、国際ロビー活動を行う予定です。
質問4:活動をしている中でパートナーシップの重要性や課題について、普段から思うことや心掛けていることなどについて教えてください。
子どもケミネット自体がネットワーク組織ですので、加盟団体・個人、専門家の方々と連携・協力しながら課題に取り組んでいます。研究者をはじめとした専門家の方々から指導・助言が得られることはとても大きいです。また、なにより大事なのは、参加しているメンバーそれぞれが、主体的に取り組み、行動提起につなげていくことだと思います。それぞれが「感じ、考え、行動する」こと。そして、感じたことを共有し、議論を尽くし、行動することで、より創造的で広がりをもった活動につながっていくと感じています。
子どもケミネットの趣旨に賛同される方は、ぜひ子どもケミネットにご参加ください!皆様からの主体的参加をお待ちしております。
参考サイト:
▼ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議(JEPA)
https://kokumin-kaigi.org/
▼「プラスチックに含まれる有害化学物質―要約と主要なポイント―」
https://kokumin-kaigi.org/?page_id=10921
▼なお、原版をご覧になりたい方は、UNEPのホームページをご覧ください。
https://www.unep.org/resources/report/chemicals-plastics-technical-report
▼有害化学物質から子どもを守るネットワーク(子どもケミネット)
https://c.kokumin-kaigi.org/

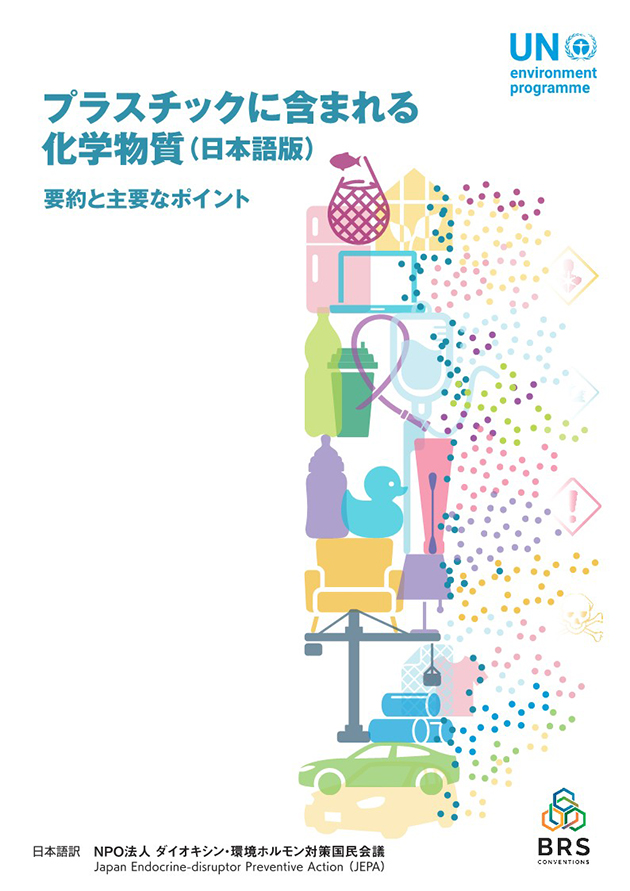
プロフィール:成嶋悠子(なるしま ゆうこ)
 弁護士、ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議(JEPA)理事、有害化学物質から子どもを守るネットワーク(子どもケミネット)世話人、グリーン連合幹事、オーフス条約を日本で実現するNGOネットワーク(オーフス・ネット)運営委員
弁護士、ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議(JEPA)理事、有害化学物質から子どもを守るネットワーク(子どもケミネット)世話人、グリーン連合幹事、オーフス条約を日本で実現するNGOネットワーク(オーフス・ネット)運営委員
